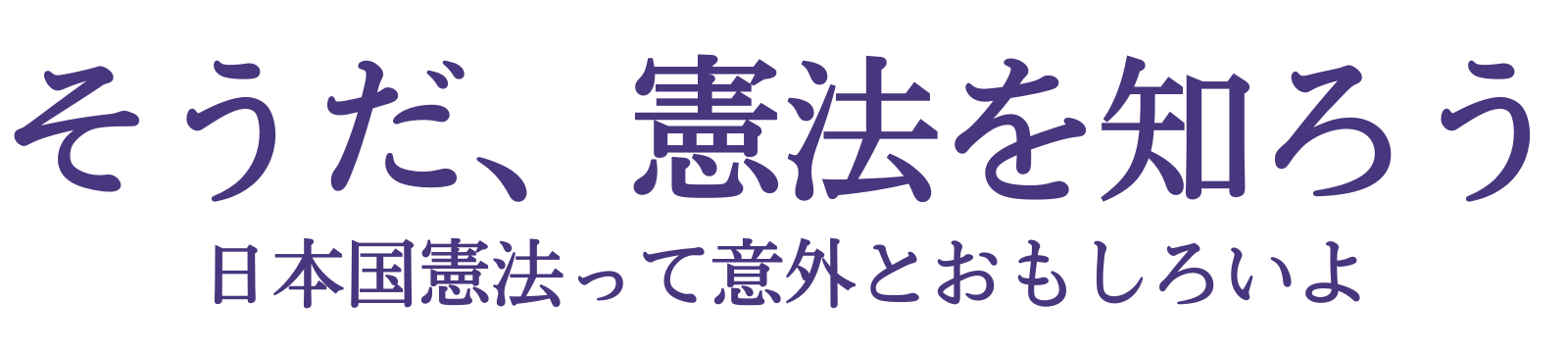たとえば、学校で行われる文化祭を思い出してみて。
文化祭全体の方向性やメインの企画などの
柱、大筋を考えるのは生徒会(または文化祭委員会)。
全体のルールを決めるのは先生たち。
(予算はいくらだよ、開催日はいついつ、
こういうのは禁止ね、とか)
じゃあ実際に細かい単位で企画を立てたり、
学校中の飾りつけをしたり、お店を動かしたりするのは?
文化祭を実際に盛り上げるのは?
そう、現場で動くのはクラスのメンバー、
つまり“実行する人たち”だよね。
政治の世界でも、同じような分担がされているんだ。
法律を作るのが国会(立法)、
ルールを守ってるかチェックするのが裁判所(司法)。
そして実際に政策を実行するのが内閣。
これを「行政権は内閣に属する」って憲法第65条が決めているんだ。
え?たった一行だけ?
って思った?
でもこの一行、実はとっても重要な意味を持っているんだよ。
これについて、天使くんと悪魔くんが話してくれているから、
是非最後まで読んでいってね!
第65条【行政権の帰属】
行政権は、内閣に属する。



悪魔くん、今日は日本国憲法第65条について話そう!
まずはさ、意訳してみてよ



つまりだ、政治を実際に動かす「行政の力」は、
全部まとめて内閣がやるって話だ。
法律を作るのは国会、裁判は裁判所。
で、残った実行部隊が内閣ってわけだな。
まぁ要するに、動かすのは俺たちってこった。



うん、意外とちゃんとわかってるね。
政治を動かす役目は内閣がやりますよ、ってことね。



でもさ、内閣がやるってことは、
総理大臣の言うことが絶対ってことか?
だったら俺、もっと総理にガツンとやってもらいたいねぇ。
国のトップなんだし、細かい手続きなんかすっとばしてさ。



ああー、それはちょっと違うかな。
この条文はむしろ、
「内閣には行政しかやらせない」っていう制限の意味があるんだ。
内閣に全部まかせたから、他は手出しするなって意味じゃないよ。



は?どういうことだよ。
「内閣に属する」って書いてあるだろ。
それって、力を集めたってことじゃねぇの?



そう見えるけど、実はこれ「消極的な定義」って言われてるんだ。
たとえばね、昔の王様って、
・立法(法律を作る)
・司法(裁判をする)
・行政(実行する)
ってのを全部やってたでしょ?
でもそれじゃ独裁になっちゃうから、
憲法では「じゃあ内閣は行政だけね」って分けたわけ。



立法は国会、
司法は裁判所、
で、残ったのもを内閣に、って感じだから。
内閣を優先!というわけではないんだ。



なんだよ、消極的って。
結局、力が弱いってことか?



そう。わざとそうしてるんだよ。
総理大臣や内閣が勝手に突っ走らないように、あえて力を分けてるの。



でもさ、最近の改憲案だと、
総理の「専権事項」ってやつが増えるとか言ってなかったか?



そうだんだよ。そこが問題なんだ。
自民党の改憲草案では、今のシンプルな条文に、
「ただし、特別な場合はこの限りじゃない」っていう、
余計ない一文を入れようとしてるんだ。



それってどうヤバいんだ?



その「特別な場合」ってのがクセモノでね。
たとえば、国防軍の指揮権、衆議院の解散権とか、
総理一人だけが判断できることが増えちゃう。
つまり、「内閣みんなで話し合って決めよう」じゃなくて、
総理ひとりの独断で政治が動く可能性が出てくるんだよ。



なるほどな……
たしかに、トップに力を集めすぎると、
独裁まっしぐらって気もするな。
昔みたいに戦争に突っ走るってことも、
ないとは言えねぇか。



うん。第65条は、短くて地味に見えるけど、
政治の暴走を止めるブレーキのひとつなんだ。
だからこそ、この条文を変えるってことには
慎重にならなきゃいけない。



そっか。
今の憲法は「全部やっていい」って意味じゃないんだな。
なんか、憲法って、やっぱり「偉い人を縛るためのルール」なんだな。



そういうこと!
まとめ
第65条はたった一文、「行政権は、内閣に属する」。
たったこれだけの文章なのに、天使と悪魔の会話を通して見えてきたように、
この条文には、私たちの自由や安全を守るための仕組みがギュッと詰まっています。
最近は、「総理大臣にもっと力を持たせたほうがいい」っていう意見も聞きます。
でも、力を集中させるってことは、それだけ危険も大きくなる。
だからこそ憲法は、あえて“力を分ける”ように作られているんです。
第65条はその分け方のひとつ。
内閣がやるのは、あくまでも行政だけ。
法律を作ったり、人を裁いたりするのは別の機関がやる。
これが、私たちの暮らしを守る「三権分立」という考え方です。
憲法って、難しい言葉ばかり並んでいるように見えるかも。
でも、実は「誰かが勝手に物事を決めないようにする」ためのルール。
つまり、偉い人たちの“暴走”を止めるブレーキなんだ。
これもそうだよ!