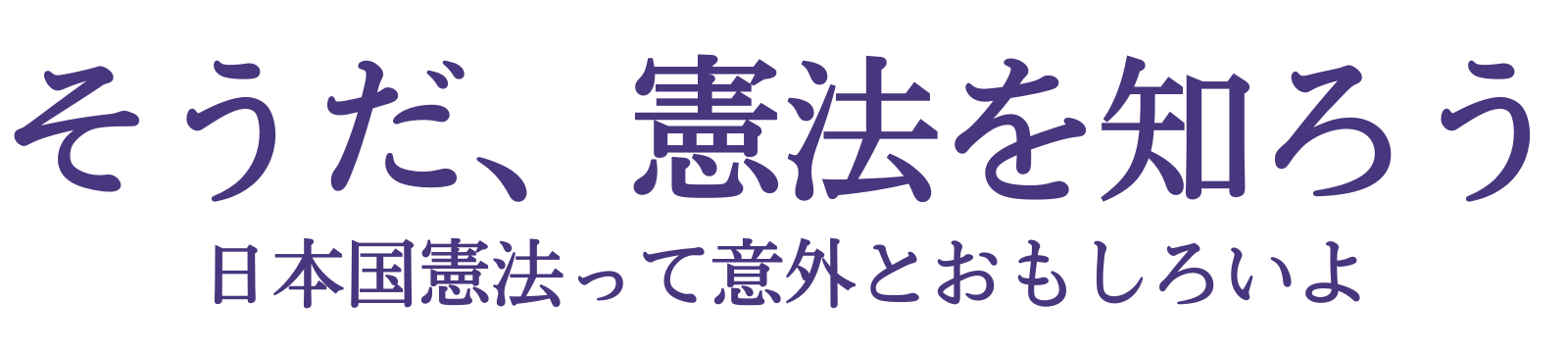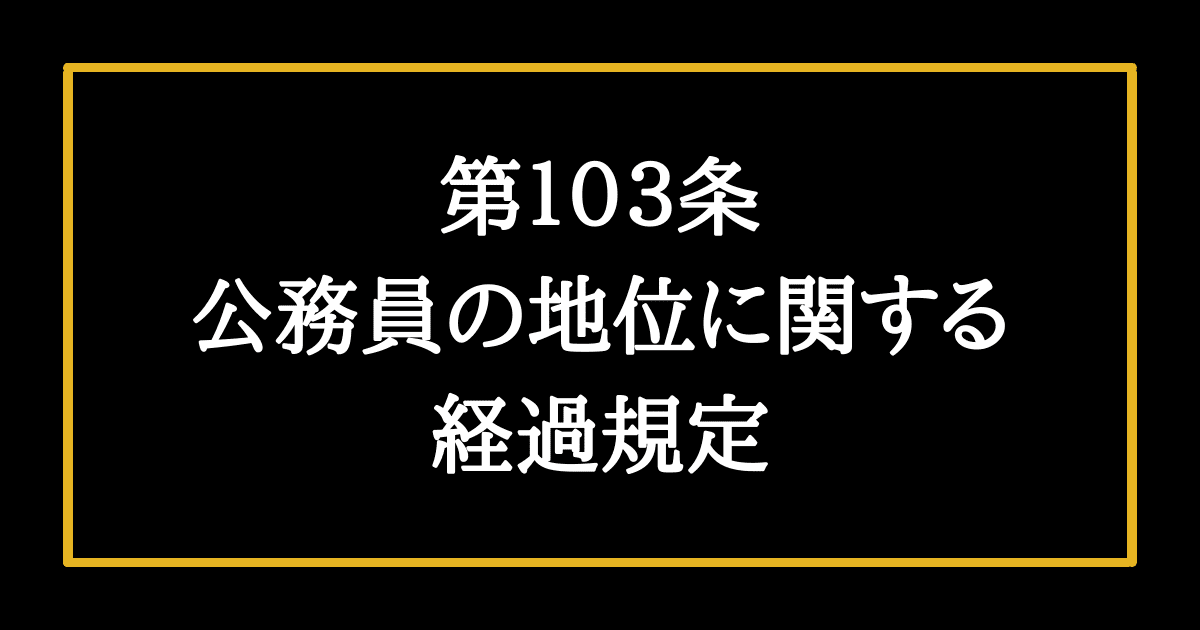こちらは日本国憲法第103条の解説記事です。
この第103条が伝えたいポイントというのは……
具体的にはどういうことなのか?というのを解説していきます。
ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!
日本国憲法第103条【務員の地位に関する経過規定】
意訳
原文
日本国憲法第103条を更に深堀してみよう
要点①:参議院議員はどうなったのか?
この条文には参議院議員については書かれていませんね。
それは、それまでの明治憲法では「貴族院」であり、この日本国憲法施行をもって廃止されたからです。
そして代わりに新設されたのが「参議院」です。
そんな参議院が憲法施行日までに成立しなかった場合は?
その時は成立するまでは衆議院だけで国会を運営するよう、第101条にて補則されています。
この条文には参議院議員については書かれていませんね。それは、それまでの明治憲法では「貴族院」であり、この日本国憲法施行をもって廃止されたからです。
そして代わりに新設されたのが「参議院」です。
そんな参議院が憲法施行日までに成立しなかった場合は?その時は成立するまでは衆議院だけで国会を運営するよう、第101条にて補則されています。
要点②:本来であれば……
大日本帝国憲法のもとでは、主権は天皇陛下にありました。
そして、公務員たちは皆「天皇陛下に奉仕する者」だったのです。
ですが、日本国憲法に伴い「民主主義体制」に変わりました。
それはつまり、主権も天皇から国民に変わったということです。
よって、本来であれば、
「全員、一旦は公務員の地位から外れたうえで、新憲法における主権者(国民)によって新たに選び直される」
のが筋のはずですが、そうはなりませんでした。
ここは「国政の急激な変化を避けるために、人員の交替は穏健に」という思惑が働いていたと言われています。
例えば企業のM&Aの後、買収された側の会社の役員たちが全員その任を解かれるかといったら、
そうでもないのと同じようなものかもしれません。
とはいえ、現在の日本の状態から考えると、全員解任したほうがよかったのではないか。
そして、戦争に加担した責任を負うとして被選挙権の資格さえも奪った方がよかったのではないかと、
個人的にはそう思っています。
大日本帝国憲法のもとでは、主権は天皇陛下にありました。そして、公務員たちは皆「天皇陛下に奉仕する者」だったのです。
ですが、日本国憲法に伴い「民主主義体制」に変わりました。それはつまり、主権も天皇から国民に変わったということです。
よって、本来であれば、
「全員、一旦は公務員の地位から外れたうえで、新憲法における主権者(国民)によって新たに選び直される」
のが筋のはずですが、そうはなりませんでした。ここは「国政の急激な変化を避けるために、人員の交替は穏健に」という思惑が働いていたと言われています。
例えば企業のM&Aの後、買収された側の会社の役員たちが全員その任を解かれるかといったら、そうでもないのと同じようなものかもしれません。
とはいえ、現在の日本の状態から考えると、全員解任したほうがよかったのではないか。そして、戦争に加担した責任を負うとして被選挙権の資格さえも奪った方がよかったのではないかと、個人的にはそう思っています。
この第103条の改憲草案はどんな内容?
この条文は現憲法を施行した時の「補則」のため、改憲草案の対象外です。
後記
国政に空白期間ができることによって混乱が起きるのを避けるための条文でした。
第100~103条はこのように日本国憲法施行までの間の混乱を避けるための努力が見られます。
繋がりのある条文
この第103条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第103条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました!