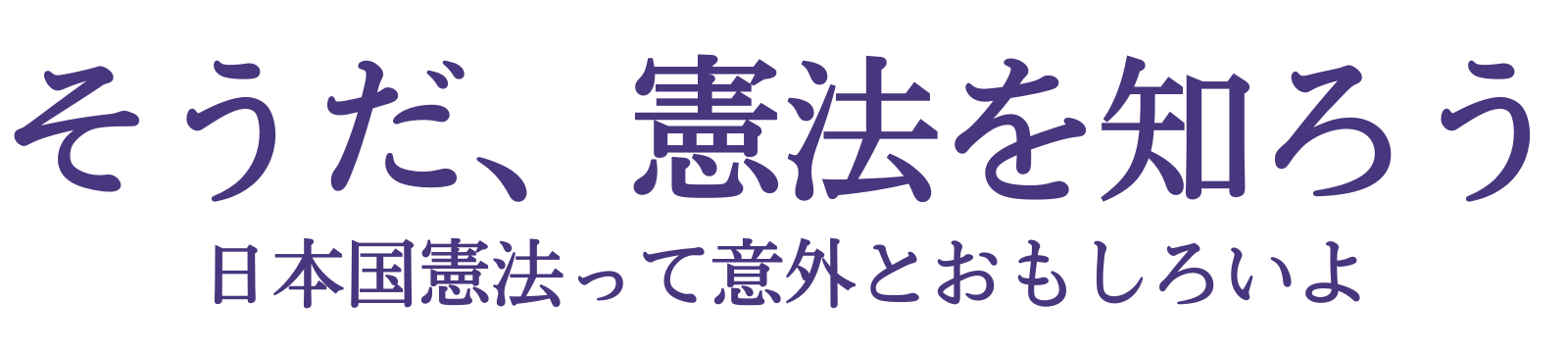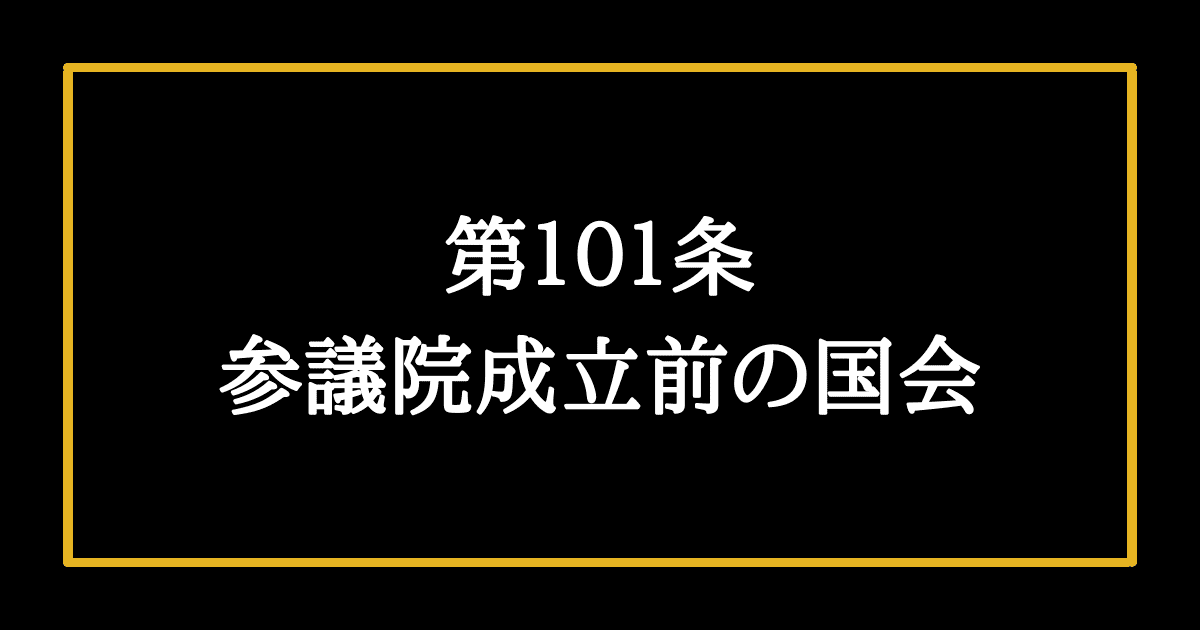こちらは日本国憲法第101条の解説記事です。
この第101条が伝えたいポイントというのは……
具体的にはどういうことなのか?を解説していきます。
ぜひ最後まで読んでもらえたら嬉しいです!
日本国憲法第101条【参議院成立前の国会】
意訳
原文
日本国憲法第101条を更に深堀してみよう
要点①:実際は施行前に参議院も無事成立した
実際は、日本国憲法が施行される前に参議院が無事成立したため、
この規定は遂行されることはありませんでした。
実際は、日本国憲法が施行される前に参議院が無事成立したため、この規定は遂行されることはありませんでした。
1946年(昭和21年)
11月3日:日本国憲法公布
1947年(昭和22年)
2月24日:参議院議員選挙法公布・施行
3月31日:衆議院解散(帝国国会の終幕)、改正衆議院議員選挙法公布
4月20日:第1回参議院選挙
4月25日:第23回衆議院議員総選挙
5月2日:貴族院の廃止
5月3日:日本国憲法施行
5月20日:第1回国会召集
要点②:明治憲法では「衆議院・貴族院」の二院制
明治憲法(大日本帝国憲法)では「衆議院・貴族院」の二院制でした。
その貴族院というのは、皇族・華族や高額納税者など選挙で選ばれていない議員で構成されていました。
そのため、貴族院は民主主義にはふさわしくないということで廃止され、
参議院の議員も国民から選挙によって選ばれることになったのです。
ちなみに衆議院は明治憲法の時も選挙で選ばれた人たちで構成されていましたので続行となりました。
明治憲法(大日本帝国憲法)では「衆議院・貴族院」の二院制でした。
その貴族院というのは、皇族・華族や高額納税者など選挙で選ばれていない議員で構成されていました。そのため、貴族院は民主主義にはふさわしくないということで廃止され、参議院の議員も国民から選挙によって選ばれることになったのです。
ちなみに衆議院は明治憲法の時も選挙で選ばれた人たちで構成されていましたので続行となりました。
明治憲法の下での選挙権について
当初は「直接国税を15円以上納める男性」だけであり、
実質選挙権を持っていたのは人口の1.1%しかいませんでした。
※15円……現在で言えば60~70万円
1925年(大正14年)には、25歳以上の男性全員に与えられました。
そして1945年(昭和20年)、ついに20歳以上の男女全員が選挙権を持てるようになりました。
当初は「直接国税を15円以上納める男性」だけであり、実質選挙権を持っていたのは人口の1.1%しかいませんでした。
※15円……現在で言えば60~70万円
1925年(大正14年)には、25歳以上の男性全員に与えられました。
そして1945年(昭和20年)、ついに20歳以上の男女全員が選挙権を持てるようになりました。
要点③:実は総司令部(GHQ)は一院制を打診していた
実は当初、GHQからは一院制を打診されていました。
それに対して、日本側が二院制を主張していたのです。
ですが、これは「貴族院」を残す形での二院制でした。
貴族院は民主化推進にふさわしくないと、当然反対されました。
折衝の結果、貴族院の廃止・公選による参議院の設立という形でGHQに認めさせることになります。
日本政府内においても「貴族院がなくなるのであれば一院制で十分ではないか」という声があがったそうです。
ですが、これに対しては
「参議院は一種の抑制機関である」
「多数党の一時的な勢力による弊害を防止するものである」
と、金森国務大臣が答弁したことにより、「衆議院・参議院」の二院制が無事成立しました。
実は当初、GHQからは一院制を打診されていました。それに対して、日本側が二院制を主張していたのです。
ですが、これは「貴族院」を残す形での二院制でした。
貴族院は民主化推進にふさわしくないと、当然反対されました。折衝の結果、貴族院の廃止・公選による参議院の設立という形でGHQに認めさせることになります。
日本政府内においても「貴族院がなくなるのであれば一院制で十分ではないか」という声があがったそうです。ですが、これに対しては
「参議院は一種の抑制機関である」
「多数党の一時的な勢力による弊害を防止するものである」
と、金森国務大臣が答弁したことにより、「衆議院・参議院」の二院制が無事成立しました。
この第101条の改憲草案はどんな内容?
この条文は現憲法を施行した時の「補則」のため、改正草案の対象外です。
後記
万が一の事にも備えての補則、こういったことも想定していたのですね。
そして貴族院が廃止されて本当によかったです。
(貴族院を残したかったという性根は今も残っていますが)
万が一の事にも備えての補則、こういったことも想定していたのですね。そして、貴族院が廃止されて本当によかったです。
(貴族院を残したかったという性根は今も残っていますが)
繋がりのある条文
この第101条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
この第101条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。(リンクの文章は記事のタイトルではなく、関連がわかるような紹介文にしています)
興味のあるところを是非。
最後まで読んでくださってありがとうございました!